promotion
家の設計と同様、外構をどのような資材を用い、どのように仕立て上げるのかを決める図面があります。
これを「外構図(外構図面)」と呼びます。
プライバシーの問題や季節感の演出といった必要に応じて、植栽を含めることもあります。
この記事では外構図について解説していきます。
リフォームを考えているあなたは今、「リフォーム会社が多すぎて、どこにお願いしたら良いか分からない」と悩んでしまってはいませんか?
リフォームにはたくさんのお金を使いますし、失敗して後悔したくはありませんよね・・・。
そんなときに「絶対使わないと損する」サービスがあるんです!
それが、リクルートが運営するSUUMOカウンターリフォーム。

◼️完全無料
◼️無理な営業は一切なし
◼️優良なリフォーム会社800社から厳選して紹介
◼️万が一でも安心な「完成あんしん保証」付き
◼️お断りも代行してくれる
◼️相談だけでもOK
自分ではなかなか会社選びが難航してしまいますよね・・・。でもこのSUUMOカウンターリフォームを使えば、プロが一瞬でおすすめの会社を複数紹介してくれるので、忙しい人でも簡単にリフォーム会社を比較検討できるようになりますよ!
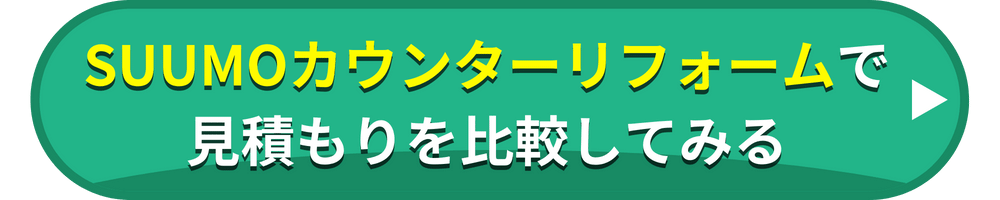
外構図は、家を取り巻く敷地の設計図
家は建物だけでは成立しません。
たとえ敷地ぎりぎりに建てる家であっても、上下水道の管の敷設といったインフラ面での外構も必要です。
敷地がある程度確保できる場合は、最低限でも駐車場(カーポート)や門から伸びるアプローチ、プライバシー保護のための塀や生け垣が必要です。
これらをどんな材料でどのように仕上げるのかの設計が外構図ですから、建築家に家と同時に考えてもらうのが通常です。
- 外構図は建物の外側の外構に関する設計図
配置図との違い
外構図と似ている物に「配置図」というものがあります。
配置図は、敷地の形状や建物の位置、隣接する道路との関係を示した図面のことです。
名前の通り、何がどの方向に「配置」されているかを表しています。
敷地、建物、道路の関係性を見ることができます。
一方、敷地内の建物以外の部分、つまり外構部分についての詳細を記した図面になります。
外構図の記号や数字の見方

外構図は主に3種類あります。
- 平面図:上から見た基本の図面
- 立面図:高さが分かりやすいように横から見た図面
- パース:立体的な全体像が分かるように示した図面。出来上がりのイメージ図。
この中で、一般的に一番細かく記載されているのが平面図。
平面図には外構の仕様が記載されており、現場の職人もこの外構図を見ながら作業を進めていきます。
この外構図の中で、最低限押さえておきたい「見方のポイント」は2つ。
サイズと高さです。
サイズを見る:縮尺・スケール
外構図からサイズを見るには「縮尺」を確認します。
平面図の下のほうに、「S=1/100」などと記載されている場所があります。
この場合は1/100が縮尺、つまり実際の大きさの1/100の大きさで描かれているということになります。
高さを見る:ベンチマーク(BM)
外構図において高さは「+100」「+150」などの数字で示されます。
これは、基準となる地点を0として、そこからの高さを表しています。
敷地内の1か所に「BM±0」と記載されている場所が基準の場所です。
水はけが必要な場所では必ず勾配を付けているはずですから、どの程度の高さで勾配をつけているかが、この記載から分かることになります。
また家本体(建物)の地盤の高さは「GL」として表され、例えば「GL=BM+200」あれば建物の地盤の高さは基準地点から200高い位置にあるということを表します。
外構を施工させるためのコツ2つ

家をより美しく・楽しくする外構は専門家の知恵が必要
「エクステリア」というキーワードで画像を検索すると、施工事例の写真が多く見つかります。
ざっと眺めるだけでも、多種多様な仕立て方があることが理解できます。
そのいずれもが家を美しく引き立てていますし、敷地を効率的に活用する知恵であふれています。
シンボルツリーや外部からの視線・直射日光を防ぐために植栽を行っている写真もあります。
これはその木の性質も含め、活用方法に適した木を選定しています。
家にマッチした塀や樹木は、美観と同時に機能をも考え合わせる必要があり、専門知識が求められるものなのです。
使用してほしい「代々伝わる庭石」や「樹木」があるかもしれません。
これらを含め、家と外構のイメージをうまくなじませるのも建築家や外構業者のセンスです。
DIY派であっても、専門家にアドバイスをもらって
予算の都合で外構は自分で、とおっしゃる方もいらっしゃいます。
また、自分も家づくりに参加したいと思うDIY派の方にとって比較的ハードルの低い部分が外構であることから、「手作りしたい」と希望されることもあるでしょう。
こういった場合も、建築家にイメージ合わせのためにどのような資材を用いたらよいのか、DIYに必要なレンタル機器はないかといった大まかな相談をしておいた方が安心です。
気づけば家と外構のイメージがなんとなくちぐはぐ…という問題を招かずに済みます。
個人でも買えるものを上手く組み合わせるコツもアドバイスしてもらっておくと不安もなく取り掛かれるでしょう。
後々の相談にも乗ってもらえるよう、約束を取り付けておいてもよいかもしれません。
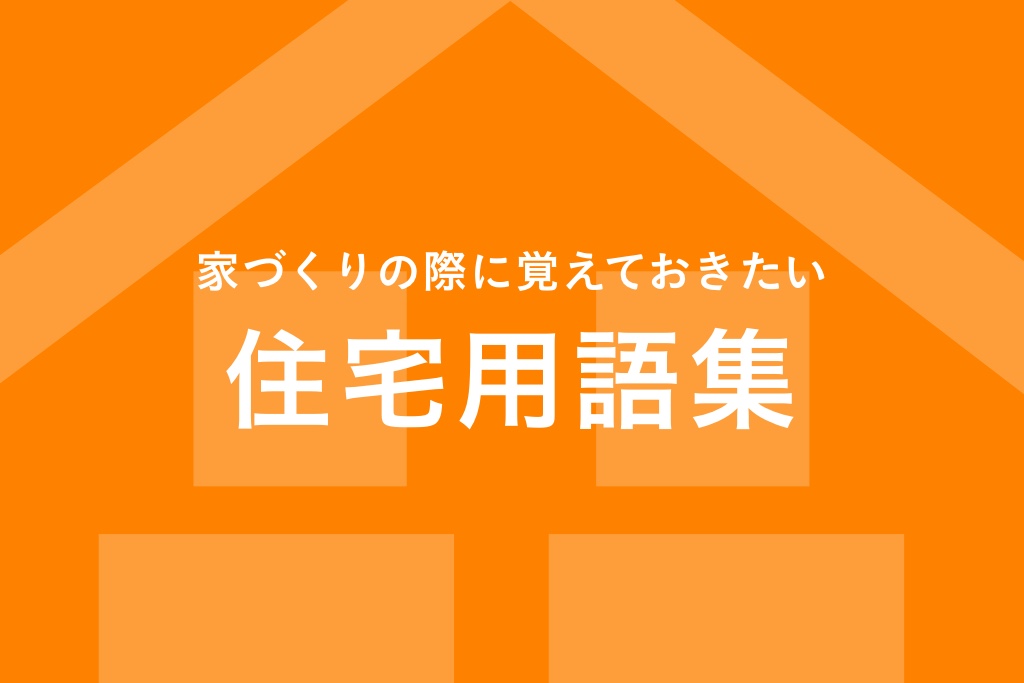



コメント